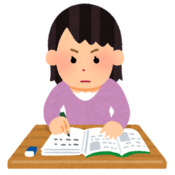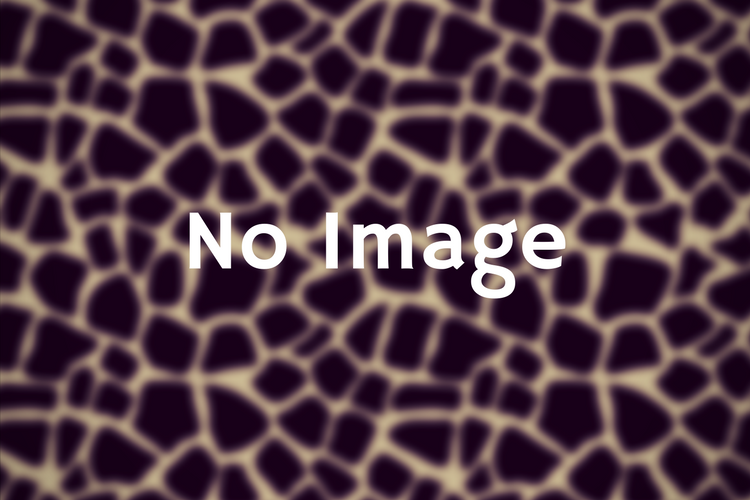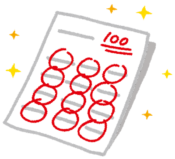たし算、ひき算から始まる計算の工夫

こんにちは。TANUKIです。
今回は低学年算数で最も大切といっても過言ではない計算の工夫についてです。
低学年の子は計算が好きな子が多いです。
算数=計算だと認識していて、計算が得意な自分は算数が得意だと思っています。
しかし学年が上がるにつれて思考力が問われるようになってくると算数と計算が必ずしも同じではないことに気がついて算数が苦手になっていきます。
それを防ぐいい手があります。
計算を使って思考力をつけましょう。「計算の工夫」です。
「工夫しなくても出来る」は「工夫ができない子の言い訳」です。
自転車に乗れない子が乗り方を覚えるより歩いた方が早いと言ってるのと同じです。
計算が得意な子は、そこに工夫を身につけることで計算力の更なる強化と、思考力の強化にもつなげましょう。
逆に計算が苦手な子も工夫のレベルが高ければ計算が得意だった子を抜くことが可能です。
さらに頭を使うことで計算が楽しくなります。
低学年の子にとって計算の工夫は最も効果的な学習です。
今回はその入門編です。
1、たし算を工夫する
2、ひき算を工夫する
3、切りのいい数から引く
という段階を踏んでステップアップしていきます。
1、たし算を工夫する
97+54と100+51のどちらが簡単かわかりますか?
と聞くとほとんどの子が100+51の方が簡単だと答えます。
この結果が同じ理由を考えさせます。たし算は合わせることが目的なので、54から3あげてから足しても変わらないわけです。
2、ひき算を工夫する
そのまま流れで126-98
を工夫してみようと告げるとかなりの子が126から98に2移します。
引き算はちがいを比べるのでそれではおかしいということを学びます。
たし算と同じく、引き算そのものの意味を考えながら工夫することを覚えていきます。
3、切りのいい数から引く
10000から4256を引く計算。おつりの計算です。
普段買い物をする大人なら当たり前に出来るこの計算が子どもには難しいです。
一の位以外で9をつくって一の位で一気に繰り上がるような数を考えます。
10000と4256でしたら上から5740で9990をつくって最後の桁で繰り上がります。
大きな数でもできるのでこれを教えると喜んで計算したがります。
これを知らないまま高学年になるケースもあるのでしっかり意識したいです。
これらの計算を、普段の計算で常に意識しましょう。
普通の解き方と工夫する解き方両方やってみることを日課にしておくと間違いが格段に減りますよ。
こちらもあわせてどうぞ
かけ算の筆算と九九を暗記する前に触れたい計算の工夫~限定無料問題集付き×2編
かけ算ですが、最初の導入にぴったりの×2の練習用です。
九九ではなくいきなり2けたや3けたの数が登場しますが、暗記が目的ではないので問題なく計算できます。
【無料有り】計算の工夫を極める問題集がついに完成しました。【半額有り】
いま一番売れています。
中学受験で必要な計算の工夫をすべて学習できる計算プリントです。
対象学年は4~6年なのでこの記事に書いてあるレベルよりもう少し上になりますが、市販のどの問題集にもこのレベルの問題はありません。おすすめです。